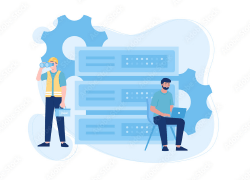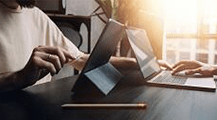サイバーセキュリティとは?
必要とされる背景や、対策方法を解説
更新日:2024-11-08
- セキュリティ

サイバーセキュリティとは
サイバーセキュリティとは、コンピュータシステム、ネットワーク、データを不正アクセスや攻撃から防御することです。サイバーセキュリティの主な目的は、機密性、完全性、可用性の3つの要素を確保することです。これにより、情報が適切に保護され、必要なときにアクセスできることが保証されます。
企業にとってサイバーセキュリティを確保することは、顧客や取引先のデータを安全に保つことで信頼を維持し、ビジネスの継続性を確保することに繋がります。また、サイバー攻撃による経済的損失やブランドイメージの低下を防ぐことができるため、長期的な視点で見ればコスト削減にもつながります。さらに、個人にとっては、個人情報やプライバシーの保護が強化されることで、安心してインターネットを利用することが可能になります。
このように、サイバーセキュリティは現代社会において不可欠な要素であり、技術の進化に伴ってその重要性はますます高まっています。各組織や個人が適切な対策を講じることによって、デジタル世界での安全性を確保し、安心して生活やビジネスを営むことができるのです。
サイバーセキュリティが注目される背景
世界的なデジタル社会の構成によりインターネットとコンピュータは進化を続け、周りにはコンピュータ制御されたものやサービスがあふれ、IT技術を駆使して利便性が追及された私たちの生活環境は大きく変わりました。
しかし、サイバー空間には国境も法規制もなく、IT技術を悪用して不正行為を繰り返す人間がいます。企業や組織の機密情報を盗み、不正に金銭を奪取するサイバー攻撃が年々増加しています。
サイバー空間は「陸」「海」「空」「宇宙」に続く「第五の戦場」として定義されていて、国家間のサイバー戦争も発生しています。
年々増加するサイバー攻撃に対して、私たちはどのような対応を採る必要があるのか、真剣に向き合う必要があります。

サイバー空間に存在する脅威情報
サイバー攻撃の増加に伴い、サイバー空間にさまざまな脅威情報が存在するようになると、その脅威情報を売買する闇市場が形成されるようになりました。そこにはサイバー攻撃で奪われた各種情報やハッキングに関連する技術情報、さらには流出情報を利用した2次攻撃の手法やサイバー犯罪に関わる闇ビジネスの手引きなど、さまざまな脅威情報が氾濫し売買されています。
このような闇市場は、Webのしくみでアクセスする「ダークウェブ」と呼ばれる闇サイトが20年程前から存在していましたが、最近はSNSなどのメッセージングアプリケーションを利用した「ブラックマーケット」と呼ばれる闇チャネルが急増し、ハッキンググループなどのサイバー攻撃者やIT技術を不正に利用して金品を奪い取る闇ビジネス事業者などが多数利用しています。闇市場は秘匿性が高く、その存在自体がサイバー空間にあることから特定が難しく、特に「ブラックマーケット」と呼ばれる闇チャネルは、この数年で膨大な数のチャネルが生成されています。皆さんも最近のニュースで「SNSで勧誘され、面識のない人に指示されて犯行に及んだ」という内容を聞いたことがあるのではないでしょうか?
デジタル社会で生き抜くためには、このようなサイバー空間の脅威から被害を受けないようにすることが必要になります。

サイバーセキュリティ対策の重要性
不正アクセスによる機密情報流出やランサムウエアなどのサイバー攻撃を受けると企業や組織は大きな損失が出てしまいます。しかし、攻撃者がこのような攻撃を実行するまでには、いくつかの段階を踏んで最終目的の攻撃を行います。企業の多くは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を参考に情報セキュリティ対策を整えますが、サイバー攻撃者はこの対策を回避する攻撃を繰り返します。
実際に被害を受けた企業で担当者の中には「セキュリティ対策はしていた」というコメントも多くあり、原因不明となる場合もあります。
情報セキュリティ対策は、システムの脆弱性やリスクを分析して対策を採りますが、人間で言えば健康診断に当たり、検査して悪い箇所が発見されれば治療して正常にするという考え方です。しかし健康な人でも"インフルエンザ"や"新型コロナウイルス"などが流行すると予防しなければ感染してしまいます。
この"インフルエンザ"や"新型コロナウイルス"は外的要因で、情報社会ではサイバー攻撃に該当し、情報セキュリティ対策を行っていてもそれを回避する攻撃があれば内部に侵入されてしまいます。そこで外部からの攻撃動向を理解して対策を採るサイバーセキュリティ対策が重要になってきます。

サイバーセキュリティ対策の種類
サイバー攻撃には多くの手法や種類が存在しますが、その起点として多く利用されるのが情報窃取マルウエアによる攻撃です。このマルウエアは、メールやWebから機器に感染し、アカウント情報を窃取します。窃取したアカウント情報は"なりすましログイン"に利用され、不正ログイン後、ハッキングプログラムを使いシステムの最高権限を奪います。こうしてシステムを掌握するとネットワーク内部に次々侵入し、機密情報は流出します。さらには関連会社や取引先にまで不正侵入することも可能になります。
このように、マルウエア対策をはじめとしたサイバーセキュリティ対策は、企業や組織によって実施すべき内容は変わります。ここからは代表的なサイバーセキュリティの種類をご紹介します。
1.ネットワークセキュリティ:ネットワーク内部および外部からの不正アクセスや攻撃を防ぐためのセキュリティ対策です。ファイアウォール、侵入検知システム(IDS)、侵入防止システム(IPS)などが含まれます。
2.エンドポイントセキュリティ:コンピュータやモバイルデバイスなどのエンドポイントを保護するためのセキュリティです。アンチウイルスソフトウエアやEDRツールが含まれます。
3.アプリケーションセキュリティ:ソフトウエアやアプリケーションに潜む脆弱性を特定し、攻撃を防ぐためのセキュリティです。セキュアコーディング、ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)、脆弱性管理などが含まれます。
4.クラウドセキュリティ:クラウドサービスを利用する際のデータやアプリケーションの保護を目的としたセキュリティです。クラウドアクセスセキュリティブローカー(CASB)やSASE、SSEなどのセキュリティソリューションがあります。
5.データセキュリティ:データの機密性、完全性、可用性を保護するための対策です。暗号化、データ損失防止(DLP)などがあります。
6.アクセス管理(IAM): ユーザーの身元確認とアクセス権限の管理を行うためのセキュリティです。シングルサインオン(SSO)、多要素認証(MFA)などがあります。
このように、サイバーセキュリティには様々な種類がありますが、高度な技術を持つ攻撃者は、セキュリティ対策を回避するツールを利用してくるため、セキュリティソリューションを導入したから安心ということはありません。
高度な攻撃からネットワークや大切な資産を守ることを意識して設計されたAdapterシリーズは、正しく運用していくことでサイバーセキュリティ対策として大きな効果を発揮するセキュリティソリューションになります。
詳細については、ぜひサービスページをご覧ください。
【関連製品・ソリューション】
①マルウエア検知 QuOLA@Adapter +(クオラアダプタープラス)
サイバー攻撃者はさまざまな手段でマルウエアを送り込みます。そのターゲットは企業PCだけでなく個人のPCも狙われます。テレワーク時代に安易に個人PCを社内ネットワークに接続することは、マルウエア感染のリスクが高まります。社内に接続する機器は、一定のセキュリティ要件を満たしたものを接続許可するのが安心で、社内セキュリティ要件をチェックする検疫ソリューションは有効となります。
②正規アカウント認証 Account@Adapter+(アカウントアダプタープラス)
マルウエアにより流出したアカウント情報を利用して"なりすましログイン"を行うサイバー攻撃者が急増しています。アカウントのID/パスワードだけでなく、接続する機器固有情報を利用したアカウント認証方法は、遠隔から操作するサイバー攻撃者の接続を排除する有効な手段です。
③脆弱性管理 VI-Engine(ブイアイエンジン)
サイバー攻撃者は内部に侵入する時はシステムの脆弱性を利用することが多くあります。日々報告される多数の脆弱性を管理し、脆弱性のない状況を保てば、内部に侵入されるリスクを低減できます。
④ログによる不正検知 LOG@Adapter+(ログアダプタープラス)
各種ログは、サイバー攻撃を受けた時の証拠保全として必要ですが、痕跡を消去するような攻撃を受けると何をされたか把握することができません。ログの管理方法を工夫するだけで、ログの保存と各種セキュリティ機器との連携による攻撃検知・遮断ができれば攻撃被害を低減することができます。