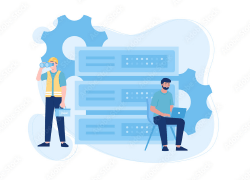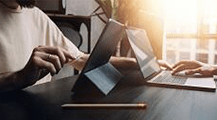脆弱性の管理とは?
必要性や対策、おすすめツールを紹介
更新日:2025-08-29
- セキュリティ
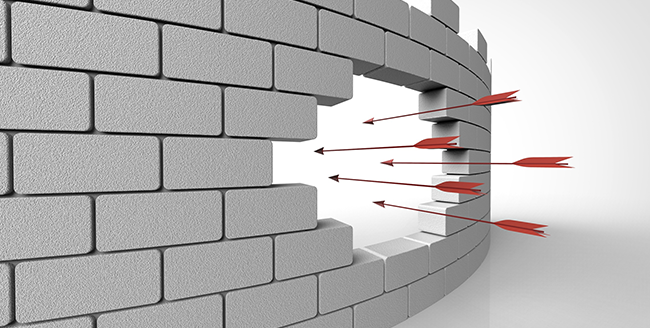
IT化が進み様々なサービスが増える中、ソフトウェアやシステムの脆弱性を狙ったサイバー攻撃が増加しています。不正アクセスによる機密情報や顧客情報の窃取、Webサービスのダウンなどの被害は後を絶たず、企業としてはイメージ低下にも繋がる危機的な状態です。今回は、そういった背景を基に重要性が高まっている脆弱性の管理について紹介します。
脆弱性管理とは
・脆弱性とは
脆弱性管理の前に、まずは脆弱性について説明します。脆弱性とは、情報ネットワークシステムに関わるセキュリティの弱点であり、攻撃を受けることによって被害を受ける危険性のことです。大きな話題となったApache Log4jの脆弱性は記憶にある方も多いかと思います。新たな脆弱性情報が知れ渡る前は攻撃する側に狙われやすいので、速やかに対策を講じる必要があります。
・脆弱性管理とは
脆弱性の管理とは何をすることでしょうか。サイバー攻撃はネットワークシステムを構築する機器やシステムの脆弱性を突いて狙ってきます。すべての脆弱性をあらかじめ把握して対処できればいいですが、なかなかそうはいきません。攻撃を受けないに越したことはないですが、それも不可能です。そこで、ツールやソリューションを用いて脆弱性をいち早く把握して対処する、それが脆弱性の管理です。様々な脆弱性管理のサービスが出ていますが、自社の課題を理解し、必要なプロセスを踏んで、適切な対応をすることが重要です。
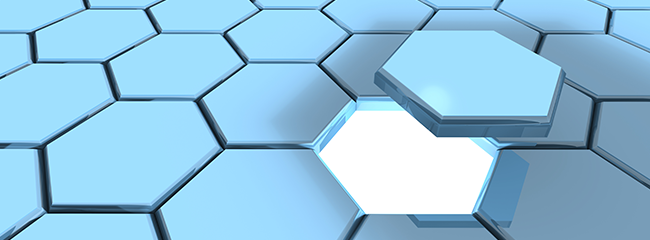
脆弱性の管理の必要性
サイバー攻撃に対しては、通信経路上で攻撃のみをシャットアウトして防ぐのが基本です。攻撃を受けることが全くなければ脆弱性管理は必要ないのかもしれませんが、残念なことにファイアウォールなどのセキュリティシステムをすり抜けてくる攻撃があり得ます。サイバー攻撃の被害報道が示すように脆弱性を完全にゼロにすることはできません。ですが、被害を受けやすい脆弱性に対処するために先手を打っておくことは重要です。経済産業省によってもサイバーセキュリティ経営ガイドラインが策定されており、企業の対応は、もはや必須とも呼べます。

脆弱性管理を実施しないリスク
脆弱性管理は実施しなくても、平時は何も問題が無いように見えますが、潜在的な大きなセキュリティリスクを抱えている状態かもしれません。ここからは、代表的なリスクをご紹介します。
・ランサムウェア攻撃
脆弱性を放置すると、それを要因にしたランサムウェア攻撃に繋がる恐れがあります。ランサムウェアは、システム内の重要なファイルを暗号化し、復旧と引き換えに身代金を要求するサイバー攻撃の一種です。これにより、業務が停止したり、機密データが利用できなくなったりするリスクがあります。
・標的型攻撃と情報漏洩
システムの脆弱性は、攻撃者が特定の組織を狙う標的型攻撃の侵入口となる可能性もあります。標的型攻撃は特定のターゲットに対してサイバー攻撃を仕掛けるもので、対象の従業員に対して、顧客や社員を装ったメールを送信しマルウェアを侵入させます。これにより、顧客データ、知的財産、企業秘密などが流出する情報漏洩に繋がり、企業の信頼性失墜や法的責任を問われるリスクが生じます。
・DDoS攻撃
トラフィック性能に関する脆弱性を利用し、大量のトラフィックを送りつける分散型サービス妨害(DDoS)攻撃を受けるリスクもあります。DDoS攻撃は、サーバーやネットワークに過剰な負荷をかけ、サービスの提供を停止させるもので、これにより、ウェブサイトやオンラインサービスが利用できなくなり、顧客満足度の低下や売上機会の損失を招きます。
・ゼロデイ攻撃
ソフトウェアの脆弱性が開発者や一般に知られる前に、その脆弱性を悪用する「ゼロデイ攻撃」に晒されるリスクもあります。ゼロデイ攻撃は、まだパッチが存在しない脆弱性を狙うため、攻撃を防御することは極めて困難です。攻撃者はこの脆弱性を利用して、マルウェアの感染、データの窃取、システムの乗っ取りなど、様々な不正行為を行います。

脆弱性管理の進め方
では実際に脆弱性管理を行う場合には、どのように進めれば良いのでしょうか。ここでは一般的な進め方をご紹介します。
ステップ1:IT資産の洗い出しと優先順位付け
まず、組織内のIT資産(サーバー、ネットワーク機器、ソフトウェア、アプリケーションなど)を洗い出し、インベントリを作成します。その上で、各資産の重要度を評価し、ビジネスへの影響度に応じて優先順位をつけます。例えば、機密情報を扱うシステムや、事業継続に不可欠なシステムは、最も高い優先度で脆弱性管理を行う必要があります。
ステップ2:脆弱性の発見と評価
次に、脆弱性診断ツールなどを活用して、特定した資産の脆弱性を定期的にチェックします。発見された脆弱性については、その深刻度(CVSSスコアなど)や悪用可能性、ビジネスへの影響度を総合的に評価し、対応の緊急度を決定します。この評価により、全ての脆弱性を順番に対応するのではなく、リスクの高いものから順に対策することが可能になります。
ステップ3:脆弱性の対応計画と実施
評価結果に基づき、脆弱性への具体的な対応計画を策定します。具体的な取り組みとしては、セキュリティパッチの適用やソフトウェアのバージョンアップなどがあります。また、すぐにパッチ適用が困難な場合は、WAFやIDSの導入などの代替策を講じて、脆弱性を放置しないことが求められます。
ステップ4:効果測定と継続的な改善
脆弱性管理は、常にリスクを抑えるために継続的に取り組む必要があります。発見した脆弱性への対策はもちろん、日々新たな脆弱性が発見されるため、定期的に脆弱性診断やリスク評価を実施することで、新しい脅威に対応できる状態を維持します。このようにPDCAサイクルを回すことで、組織のセキュリティ水準を常に最新の状態に保ち、サイバー攻撃のリスクを低減します。

脆弱性管理のおすすめツール「VI-Engine」
脆弱性が弱点となり被害を受けるリスクは分かっていながら、今まで運がよくやらなくても済んでいるため、脆弱性を放置してしまうことが多いです。脆弱性の管理は次のような点でとても面倒だからです。
・脆弱性管理には時間と手間がかかる
・脆弱性情報は増える一方
・判断して対処できる人材が限られ不足している
そのため、手間や時間をかけずに、膨大な情報の中から必要なものだけを効率的に見つけたいのが本音です。そのための脆弱性管理ツールでおすすめするのがVI-Engine(ブイアイエンジン)です。
VI-EngineのVIはVulnerability Informationの略で脆弱性情報のことで、IT資産の脆弱性を管理することに適したツールです。脆弱性情報を複数の情報源から自動収集し、指定したベンダー名や製品名などの情報をもとに必要な脆弱性情報のみを抽出できます。
IT資産の脆弱性の状況を把握して、対処の優先度付けを行い、適切な対策を迅速に行う必要があります。そのためには、日々の脆弱性情報収集が重要です。しかし、情報を理解し判断して対処できる人的リソースが量的にも質的にも不足しているのが実態です。日々の業務に追われる中、手間や時間をかけずに、膨大な情報の中から必要なものだけを見つけたいと考えているセキュリティ担当者が多いでしょう。IT資産の脆弱性情報収集にお困りのセキュリティ担当者の方にはVI-Engineがおすすめです。
【VI-Engineができること】
①IT資産に関する脆弱性チェック
②脆弱性情報のランキング付け(危険度の高い上位10件を表示)
③エンドポイントデバイスごとのOS/ソフトウェア脆弱性照会
④脆弱性対策状況のレポーティング
⑤脆弱性情報の更新に伴い、管理者へメール通知
クラウドサービスであるVI-Engineは、サブスクリプションで利用可能です。自社開発なのでカスタマイズ要望の相談も可能ですので、脆弱性管理にお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。
2022/8/18 HCNETビジネス推進グループ担当Y